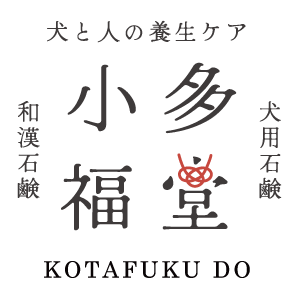2025/09/08 02:35
小多福堂では、現在、パーム油を使わない台所用石けんの製品化に向けて、試作を繰り返しています。
近年、パーム油の過剰な生産が引き起こす森林伐採や生態系破壊、そして労働環境の問題が世界的に指摘されています。
こうした課題を真摯に受け止め、人にも地球にもやさしいものづくりを目指したいと、私は考えています。
「RSPO認証」という、環境や人への配慮がされたパーム油も存在します。
石けんの素材としては固く、酸化に強いなど、優れた特性を持っています。
それでも、小多福堂はあえてパーム油を使用しません。
原材料費が値上がりし、お客様が使い続けていただくことが難しくなってしまうのです。
「食べられるくらい身近な素材だけで石けんを仕立てたい」「誰かの犠牲があったかもしれないという不安を抱えたくない」。
そんな想いから、オリーブ油や米油、ひまわり油といった食用グレードの油脂だけを選んでいます。
石けんはただ作って終わりではなく、きちんと測定して安全性や品質を確認することが大切。だからこそ、試作を重ねながら「これなら自信を持って届けられる」と言える処方を探しています。
RSPO認証と表示のルール
RSPO認証を受けたパーム油は、環境や人に配慮して作られる「持続可能な素材」として国際的に評価されています。
仕入れのときには、認証品であることを示す証明書を受け取ることができます。
ただし、実はこの証明書をそのままお客様に見せることはできません。
認証ロゴやマークを使うには、別途ライセンス契約が必要で、世界的に統一されたルールで運用されています。
だから「RSPO認証」と表示している製品は、裏側でそうした契約やルールをきちんとクリアしている、という証でもあるんです。
製品に「数字の裏付け」が必要な理由
台所用の石けんは、家庭用品品質表示法に定められた製品として扱われます。
この法律に従い、成分や量、使用上の注意などを正確に表示する義務があります。
また、景品表示法に基づき、お客様に誤解を与えないよう、製品の特長を正確に伝えることも意識しています。
たとえば、小多福堂は「犬用石けん」のお店です。犬用石けんには規制がなく、あくまで「雑貨」であり、
動物用医薬部外品やシャンプーとしての効能・効果を謳うことはできません。
そのため、効果効能を連想させる言及(例えば、「良くなったように感じる」)も雑貨で謳うことはできません。
こうした法的要件を理解し、正しい情報を伝えることで、お客様が安心して製品をお使いいただけるように努めています。
この記事でお話している「パームフリーの台所用石けん」は、試作品を外部機関に提出し、
測定データをもとに表示に必要な情報を整えます。
これは、安心して使っていただくために、「数字での裏付け」を準備する大切な仕事です。
小多福堂が純石けんにこだわる理由
多くの洗剤やシャンプーに使われる合成界面活性剤は、19世紀から20世紀にかけて広く普及しました。
特に、大量生産が容易で高い洗浄力を持つ石油系合成界面活性剤は、私たちの暮らしを便利にしました。
しかし、その高い残留性や浸透性、毒性から、下水処理で分解されにくく、河川や海を汚染する原因にもなっています。
小多福堂では、こうした環境への負荷を真剣に考え、可能な限り自然の力で分解される素材を使った製品づくりを目指しています。
今回の仕込みの様子
今回は、トマトを使ったパームフリーの台所用石けんを製造しています。
トマトに含まれるリコピンは熱に強く、石けんに色とちょっとした機能性をもたらしてくれます。
ベースのオリーブ油に、米油、ひまわり油、カカオバターなどを組み合わせ、硬さと泡立ちのバランスを調整しました。
製造した石けんは、乾燥・熟成期間を経て、品質検査のための検体となります。
「パームフリーでも、洗浄力が高く、しっかり働く石けん」であることを証明するため、数値による裏付けを取っていきます。

トマトを加える工夫と楽しみ
今回の台所用石けんには、自然の恵みであるトマトを加えています。
ただ、植物由来の素材を加えると、その分だけ「純石けん分」(石けんそのものの割合)の数値が下がります。
家庭用品品質表示法では、台所用石けんは「純石けん分98%以上」という厳しい条件を満たす必要があります。
私は、この98%の純石けん分と、水分や石けんになりきらなかった天然由来の油分で石けんを仕上げることを目指しています。
「純石けん分98%」という厳しい基準を満たすのは簡単ではありません。
でも、私は長年化粧品業界で培った経験を活かし、素材の力を生かしつつ基準をクリアする方法を探し続けています。
小さな工夫の積み重ねが、石けんづくりの楽しさなんです。
でも、私は長年化粧品業界で培った経験を活かし、素材の力を生かしつつ基準をクリアする方法を探し続けています。
小さな工夫の積み重ねが、石けんづくりの楽しさなんです。
これからのこと
小多福堂が安心できる石けんをお届けすることは、
「犬と人が、最期までともに暮らせる社会」をつくるための手段でもあります。
安心できるものを手にすることで、飼い主さんの気持ちに余裕が生まれ、その時間や心のゆとりが犬との暮らしを支えてくれる。
私はそう信じています。
安心できるものを手にすることで、飼い主さんの気持ちに余裕が生まれ、その時間や心のゆとりが犬との暮らしを支えてくれる。
私はそう信じています。